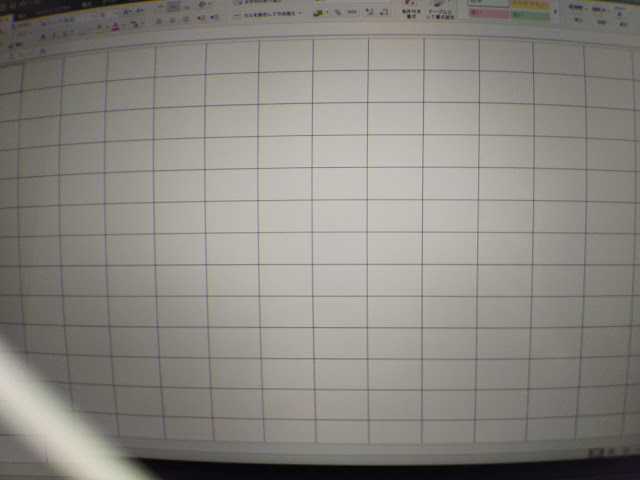SIGMAから40mm F1.4が発売された。
今回のフォトキナで発表されたレンズの中で一番期待していたものだ。発表時点からその重さ大きさ、レンズ構成、MTF曲線を見てこれは凄まじいレンズになると確信していた。CP+で発表され、実際に凄まじいレンズだった105mm F1.4と同じ雰囲気を纏っていたのだ。
まずはレンズ外観だが、今回のフォトキナ発表分のレンズからハードウェアに大きな変更がひとつあった。レンズフードだ。
フードにボタンが付き、ロックが可能になった。これによりフード紛失のリスクが大幅に減り、また花形フードでロック位置まで回さなかったことによるケラレのリスクも減った。個人的にはそのどちらも経験していないが……
SONYの135mm STFのようにロック感が皆無なフードもある中、こうした細かい部分にも配慮されているのは嬉しいところだ。
このボタンはフード内側にある爪に連動しており、ボタンを押すと爪が引っ込む。
このロック機構は特殊ネジ5本でネジ止めされており、コストが掛かっていそうだが高級感がある。
このレンズの焦点距離40mmであるが、中には中途半端に感じる人もいると思う。これはSIGMAのレンズとしては初のシネレンズ用として開発されたことに起因しており、シネレンズとしては40mmは一般的だかららしい。
しかし、スチルにおいても40mmという焦点距離は有用ではないだろうか。
私は常々「標準レンズ = 50mm」の図式に疑問を持っていた。50mm、狭くないか?
PENTAXからはFA43mmというレンズが発売されている。これは撮像面対角線長が標準レンズの焦点距離であるという考え方からきているもので、35mm判の対角線長43mmを焦点距離に持つこのレンズは「真の意味での標準レンズ」と謳われている。
また、写真はトリミングにより換算焦点距離を伸ばすことは簡単であるが、逆に換算焦点距離を縮める方向への加工はどうやったってできない。物理的に不可能である。
そう考えれば「対角線長 = 標準レンズ焦点距離」の考え方から43mmを50mmに丸めるのは意味不明。丸めるのであれば40mmにすべきだろう。
以上よりこの40mmという焦点距離こそ本来「標準レンズ」として広まっていなければならなかったのではないだろうか。私はカメラの歴史については無知なためなぜ50mmが標準になっているのか知らないが……
と、書いたはいいが現在SAマウントFoveon機に35mm判が存在しない。このレンズは来年発売する予定の35mm判Foveonで標準レンズとして使うのが楽しみだ。
(余談だが、FA43mmを「真の意味での標準」とまで謳うPENTAXが、つい最近まで自社のカメラがAPS-CだけだったのにDA28mmを出していないのも意味がわからないと思っている)
このレンズの焦点距離40mmであるが、中には中途半端に感じる人もいると思う。これはSIGMAのレンズとしては初のシネレンズ用として開発されたことに起因しており、シネレンズとしては40mmは一般的だかららしい。
しかし、スチルにおいても40mmという焦点距離は有用ではないだろうか。
私は常々「標準レンズ = 50mm」の図式に疑問を持っていた。50mm、狭くないか?
PENTAXからはFA43mmというレンズが発売されている。これは撮像面対角線長が標準レンズの焦点距離であるという考え方からきているもので、35mm判の対角線長43mmを焦点距離に持つこのレンズは「真の意味での標準レンズ」と謳われている。
また、写真はトリミングにより換算焦点距離を伸ばすことは簡単であるが、逆に換算焦点距離を縮める方向への加工はどうやったってできない。物理的に不可能である。
そう考えれば「対角線長 = 標準レンズ焦点距離」の考え方から43mmを50mmに丸めるのは意味不明。丸めるのであれば40mmにすべきだろう。
以上よりこの40mmという焦点距離こそ本来「標準レンズ」として広まっていなければならなかったのではないだろうか。私はカメラの歴史については無知なためなぜ50mmが標準になっているのか知らないが……
と、書いたはいいが現在SAマウントFoveon機に35mm判が存在しない。このレンズは来年発売する予定の35mm判Foveonで標準レンズとして使うのが楽しみだ。
(余談だが、FA43mmを「真の意味での標準」とまで謳うPENTAXが、つい最近まで自社のカメラがAPS-CだけだったのにDA28mmを出していないのも意味がわからないと思っている)
もう一点、さすがにこれに触れないわけにはいかないだろう。大きさと重さである。
本レンズはフィルター径φ82、重さが1200gだ。なんと、Artの明るい単焦点レンズの中で105mmに次いで二番目に重い。85mm F1.4と135mm F1.8ですら1130gである。発売当時、紹介するメディア全てが大きい、重いと言っていた50mmでも815gである。標準域のレンズとしては破格の大きさ、重さであろう。
この写真、左から105mm、40mm、85mmだ。
ちょっとした望遠のような佇まいである。105mmを別に重くないと言った私でも認めざるを得ない。標準レンズとしては、重い。
では、その重さと引き換えに得られる写りはどのようなものだろうか。
以下に作例を載せる。
【sd Quattro H, 40mm F1.4 DG HSM | Art 018, @40.0 mm F2.8, 1/800sec, ISO100】
【sd Quattro H, 40mm F1.4 DG HSM | Art 018, @40.0 mm F1.4, 1/125sec, ISO100】
【sd Quattro H, 40mm F1.4 DG HSM | Art 018, @40.0 mm F1.4, 1/500sec, ISO100】
【sd Quattro H, 40mm F1.4 DG HSM | Art 018, @40.0 mm F2.8, 1/60sec, ISO100】
【sd Quattro H, 40mm F1.4 DG HSM | Art 018, @40.0 mm F2.0, 1/500sec, ISO100】
【sd Quattro H, 40mm F1.4 DG HSM | Art 018, @40.0 mm F2.0, 1/400sec, ISO100】
冒頭に105mmと同じ雰囲気を感じたと書いたが、まさにそのとおり。5ヶ月前に105mmの鮮烈な写りに感動したばかりであったが、その感動をもう一度、であった。
開放から切れ味のあるピント面、にもかかわらず十分に良好なボケ。開放でも素晴らしい解像力は1段ほど絞ることで画面全域に渡って均質になり完璧と言っていい。軸上色収差も非常に少なく三枚目中央の玉ボケに多少見られる程度だ。なおこの軸上色収差はFoveonで目立ちやすく現像時にフリンジ除去を行っていないため、ベイヤーでの撮影や現像処理によってはほぼ現れないだろう。この写りは105mm F1.4がそのまま40mmになったかのようだ。
あえて弱点をあげるのならば、ボケ味は105mmにはかなわないだろうか。
しかし、1200gを持ち運ぶだけの価値はある。そもそも40mmという焦点距離で考えれば重いレンズだが、持ち運びはともかく構えて撮るときには1200g程度苦になるはずがない。
今持ち歩く単焦点を3本だけ選べというならば14mm、40mm、105mmの3本を選ぶ。この3本があれば何でも撮れそうだ。
あえて弱点をあげるのならば、ボケ味は105mmにはかなわないだろうか。
しかし、1200gを持ち運ぶだけの価値はある。そもそも40mmという焦点距離で考えれば重いレンズだが、持ち運びはともかく構えて撮るときには1200g程度苦になるはずがない。
今持ち歩く単焦点を3本だけ選べというならば14mm、40mm、105mmの3本を選ぶ。この3本があれば何でも撮れそうだ。